まずは、どのような経緯で起業されたのか教えてください。
いつも色んなことを語り合っているんですが、あるとき「最近、何かに没頭する時間が少なくなったな気がするよね」という話になり、そんなときに思い出したのは子どものころ、時間を忘れて夢中で読んだ児童文学でした。ページをめくるたびに広がる景色に心を奪われていたあの感覚を届けたい、そう考えるようになったのがハレル舎のはじまりでした。
国立を拠点にした理由を教えてください。
正直に言うと、事務所を探していた当初はそれほど場所にこだわっていたわけではありません。でも、実際に拠点を構えてみて気づいたのは、街の空気感やスピード感が日々の仕事や心のあり方に思っていた以上に影響するということでした。
国立の街には、どこかゆっくりだけれど、着実に変化していくような独特のリズムがあります。その穏やかで確かな歩みが、結果的に私たちの仕事のスタイルや価値観にぴったり合っていると感じます。
「当事者」として共に本をつくる、共創出版について教えてください。
出版には大きく二つの流れがあります。一つは、自費出版に代表される、著者自身が「こうしたい」という強い意志と資金を持ち、その意志のままに制作を進めるスタイル。もう一つは、出版社が市場や流行を踏まえて企画を立て、「こうすれば売れる」と著者に内容や表現の調整を求める企画出版です。しかし、いずれの方法でもしばしば起こるのが、責任の所在が曖昧になること。たとえば著者が、「あなたがそう言ったからこうしたのに」「売れるって言ったからそう変えた」と、選択の結果を他者に委ねてしまう。それは、著者の表現への主体性が薄れてしまうことにも繋がります。
そこで、私たちが大切にしているのが「共創出版」という考え方です。ただの自費出版でも、企画出版でもない第三の道。「おにぎりづくり」にたとえると、著者が材料を持ってきて、編集者が握るのではなくて、材料選びから始まり、握り方や味付け、海苔の巻き方まですべての工程を一緒に考え、手を動かしていく。本をつくることは、関わる全員が当事者として、迷いながら、考えながら、一緒につくり上げていくことです。

その中で一番大切にしていることは何でしょうか。
ものをつくる仕事をしていると、周囲の意見や期待に左右されることがありますよね。でも、いつも正解はわからないけど、面白いものをつくろうと思っています。
デザインや表現の世界では、“正解”は存在しません。関わる人それぞれが異なる価値観や視点を持っているけれど、面白いという感覚だけは共通認識として持てると思うんです。作り手自身がワクワクしながら取り組んでいるときって、不思議とその熱が伝わる。曖昧で確かでないものだからこそ、一冊の本をつくることに携わる全員の感覚を大切にしています。
「面白いかどうか」を指標にする、とても良いですね。
作業の途中で、「あれ?なんかつまらないな」と感じる瞬間ってありますよね。そういう違和感を見逃さないようにしています。それは自分の中にある“小さな異物感”みたいなもの。それを感じたら、必ず立ち止まって見直すようにしています。つまらないっと思いながら、なんとなく流して作業をしまうのは一番良くない。
進行中のプロジェクトでも、誰かが良かれと思って出したアイデアが、自分の中ではしっくりこないこともあります。そういうときには、あえて「それって、面白いことなんですかね?」と問いかけてみるんです。決して相手を否定しているわけではなくて、私たちがどこを目指しているのかを確認するための軸のようなものなんです。作品の「芯」になるものは、やっぱり面白さだと思うので、そこにはとことんこだわりたいですね。
面白いものには、正解の代わりに引力があります。正しくなくても、人を惹きつけて、本を手にとった人の心に残り、あとからじわじわと効いてくる。理屈では説明しきれないけれど、面白いという感覚に素直でいたいですね。

誰もが気軽に発信できるからこそ、声を発する怖さと楽しさがあります。言葉とどう向き合っていますか。
言葉にするという行為は、実はとても怖いことですよね。自分の内側をさらけ出すようなもので、誤解される可能性もある。だから、つい黙ってしまう。でも、言わないことを選び続けると、相手は何も気づかないままで、自分だけがどんどん擦り減ってしまうように感じます。
たとえば、人と関係を築くうえで、「伝えることで理解が深まるかもしれない」「共有することで関係が変わるかもしれない」と、頭ではわかっていても、その最初の一歩が怖い。でも、言葉にすることでしか、自分を知ることも、他者とつながることもできないんだと思います。
大切なのは、完璧な言葉でなくてもいいということです。正しいか間違っているかではなく「今の自分は、こう思っている」と差し出してみること。心の奥に沈殿してしまう前に、誰かに、あるいは自分自身に向けて、そっと言葉を差し出す。それが大切なんじゃないかと思っています。声に出してみたら、「あれ?こんなことだったの?」って思うこともよくあります。言葉にする勇気を持つことで、案外ラクになることも多いんですよね。
(取材ライター:Me Time Japan in Tama )
人生で影響を受けた【私の三冊】を教えてください。
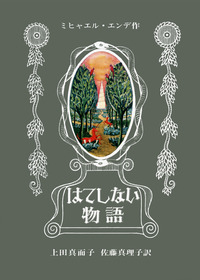
この本とは私が小学生の頃図書館で出会いました。それは赤く綺麗な表紙で、でも背はボロボロ、題字はかすれて「はてしない物語」の文字がやっと読める。おそらくたくさんの子が読んだ分だけ傷んだ姿に、むしろワクワクしました。物語を読み進めると、バスチアンという居場所のない少年が古本屋で“赤く綺麗な表紙”の本に出会う。その題字はなんと「はてしない物語」、という場面が。あれ?それって今わたしが抱えている本そのものじゃない? 思わず鳥肌。現実と物語が重なって、世界がゆがむあの感覚を味わったのは初めてでした。装丁やデザインによって人を物語に引きこむ力があること、面白さを教えてもらった大切な本です。(春山)

スイスの精神科医である著者の作品の中でもまだよく理解できてない一冊。ペルソナとは何か、誰かと話している自分は真の自分なのか、仮面をつけない自分、つまり他者が全く介在しない自分というものは存在し得るのか、などを論を読者に向けて混乱させることなく説いていく。他の著作『女性であること」や『生の冒険』にも共通しているこの世界への優しい提言が、がんじがらめになりそうな一般常識的な思考から解放してくれる。精神科医というものは患者の状況を冷静な位置から導くことが通例な中、トゥルニエは患者の苦しさの奥底まで一緒に降りていく。危険ではあるが、ここに彼の生き方というか神的視点の信仰が垣間見れる。あるべき思考に苛まれそうになる時に、読んでいると頭がガツンと砕かれる気持ちの良い良書です。理解できないままで何度も読んでいきたい。(平田)
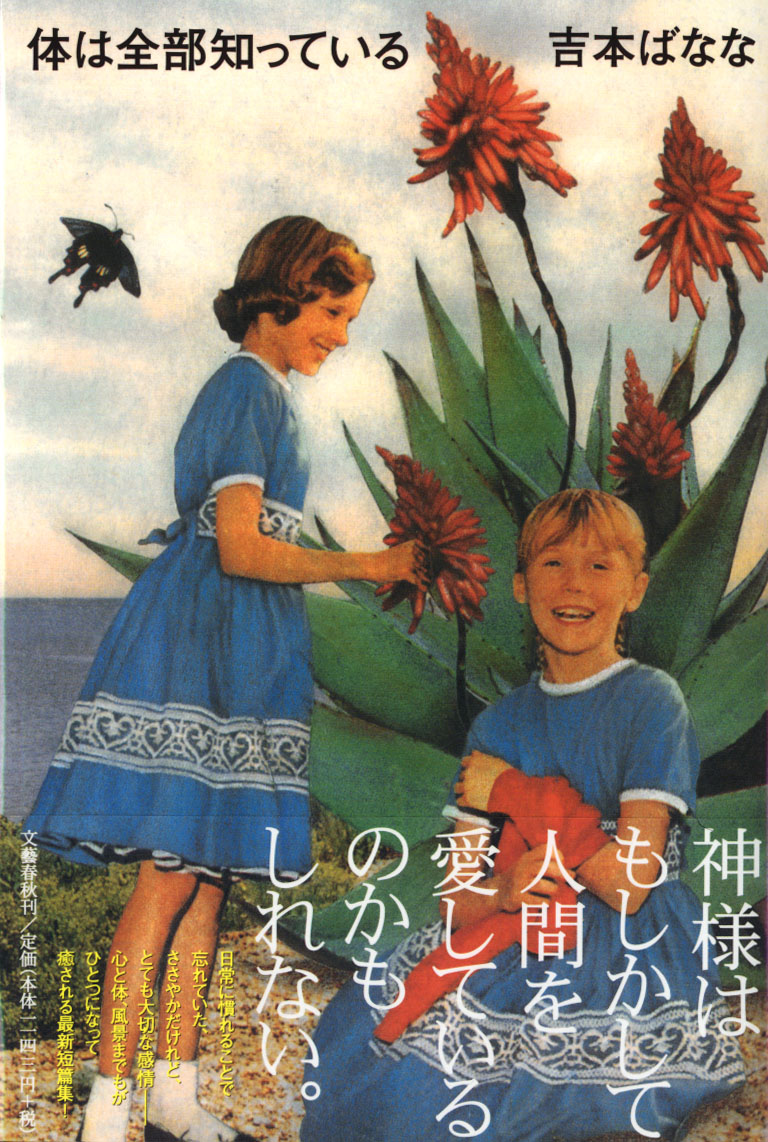
文章の巧さを改めて知らされた短編集。心の置き場所が体と繋がっていて、おざなりにされることは何も無いのだ、と思わされる。「体と本能に任せておけば、さほど間違えることはない」という一見乱暴に思える思考も、確かにその通り。やるべきことや周りの常識に翻弄されて、どれだけ体の声を聞けていないことが多いか。触れることや食べることの大切さを優しい文章で届けてくれる。「みどりのゆび」「ボート」「西日」「黒いあげは」「田所さん」「小さな魚」「ミイラ」「明るい夕方」「本心」「花と嵐と」「おやじの味」「サウンド・オブ・サイレンス」「いいかげん」の13の短編を一気に読むもよし。一つお気に入りを見つけてもよし。ばななワールドを味わって欲しい。(平田)







