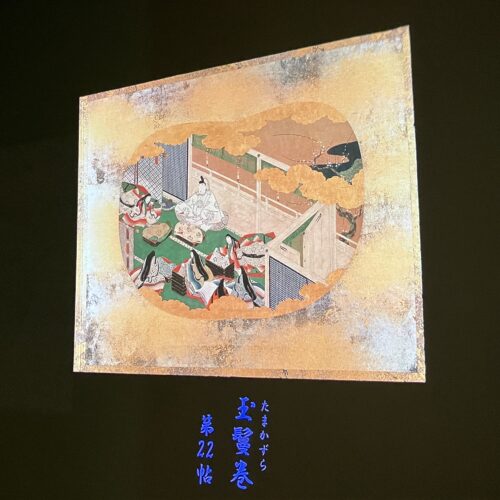東京・立川周辺のART&CULTURE情報
東京・立川周辺のART&CULTURE情報
artists

田中 麻里:Tanaka Mariアイリッシュ・ハープ奏者 https://www.harptanakamari.com/
西武多摩湖線「一橋学園駅」。
北口を降りるとすぐに、「ただいま」と言いたくなるような昔ながらの商店街がつづく。
にぎやかな商店街を抜けると、子供たちの楽しそうな声が聞こえる公園と閑静な住宅街があらわれる。
日々の穏やかな時間が流れる町。
その町の一角にスタジオをかまえる、アイリッシュ・ハープ奏者・田中麻里さんを訪ねた。
2025.07.18
普段スタジオでは、アイリッシュ・ハープやアイルランドのパーカッション教室が開かれている。また、レコーディングスタジオ、演奏のリハーサル会場としても機能している
「きれいな音だなとは思ったんですけれど」
「小学生の頃、母がハープの発表会に連れて行ってくれたんです。母は私にハープを習わせたかったみたいで。
でも、あまりピンとこなかったんです。
当時はハープを教われる先生も教室も少なく、ハープを始める前に近所のピアノ教室でピアノを習い始めたら、そのままピアノに。
母もハープのことは忘れてしまったようで、そのまま年月が経ってしまったんです」と初めてのハープとの出会いを懐かしむ。
「アイルランド音楽との出会い」
「高校生の頃はバンドを組んだり、大学生の時にリコーダーも習い始めて。
ちょうど、リコーダーを習いに行っていた教室にアイルランド音楽をやっている先生がいて、教室の合宿などに参加して仲良くなったんです。
それで、アイルランド音楽に興味を持ちました。
その時、その先生から『貴女も何かやってみてはどうかな』と、ティン・ホイッスルを勧められたのですが、難しそうだなと思って、バウロンと呼ばれる太鼓から始めたんです」と当時を振り返る。

「この楽器、ご存知ですか」
バウロン(太鼓)のビーター(バチ)が入った袋の中から、スプーンを2本取り出した田中さん。
スプーンが軽快なリズムを刻みだす。まさか、スプーンがこんなに楽しい楽器になるとは驚きである。

ピアノから始まり、バンドにリコーダー、そろそろアイリッシュ・ハープの話しかなと思えば、バウロン(太鼓)にスプーン。
なかなかアイリッシュ・ハープに辿りつく気配がないが、田中さんのリズミカルな会話に、「次は何の楽器が出てくるのだろう」と興味津々になってくる。
「アイルランドの小型ハープとの出会い」
「アイルランドの太鼓などの楽器は、いったいどこで買うのだろうと思っていたら、アイルランド音楽をやっている方の中に、古楽器やアイルランド音楽で使う楽器などを輸入している楽器商の方がいて、アメリカのメーカの小型ハープ(アイリッシュ・ハープ)も輸入し始めたんです。
バウロン(太鼓)もそのお店で購入したのですが、その小型のハープにもとても興味がわき、すぐに購入しました」とアイリッシュ・ハープとの出会いを話す。
「最初は独学だった」
高校生の頃にバンドで覚えたコード進行を使って、自分でコードを拾いながら曲を練習していった。

独学での練習だけでは壁がみえてきた頃、紹介してもらったクラシックのハーピスト(グランド・ハープの演奏者)西村光世先生、アイリッシュ・ハープ奏者の坂上真清先生に師事をし、ハーパー(アイリッシュ・ハープの演奏者)として演奏者の道を歩み始める。

「家族の転勤に伴いドイツでの生活が始まる」
「ドイツでも、ドイツ人のハープ演奏家に師事しました。
その時にアイルランドのキルケニーで行われているサマースクールをネットで見つけ、その演奏家に相談したところ、彼の友人が主宰している『Historical Harp Society of Ireland』という団体のスクールであることがわかりました。
彼が、『ぜひ行ってみては』と言ってくれたことをきっかけに参加をし、金属製の弦が張られたオールド・アイリッシュ・ハープ(クラルサッハ)の伝統的奏法を学びはじめたんです」と、所有している金属弦のオールド・アイリッシュ・ハープ(クラルサッハ)や、ナイロン弦のアイリッシュ・ハープ、ガット(羊の腸)弦のゴシック・ハープなど数々のハープを鳴らしながら演奏方法や音色の違いを聴かせてくれた。

金属弦のオールド・アイリッシュ・ハープ。爪で弾いて音を鳴らす(写真下段手前にあるハープ)
「アイリッシュ・ハープの課題」
「演奏会などで、ハープって『自由に合わせて』とか『適当にポロロロンと弾いて』と言われることがあるんだけれど」と田中さんは笑いながら話してくれたが、ハープをよく見てみると想い描くイメージとはかなり異なり、とても複雑な楽器なことがわかる。

「アイリッシュ・ハープはレバーで半音を操作する楽器で、演奏しながらの操作はちょっと大変です。
また、撥弦楽器(弦を弾いて音を出す楽器)なので、曲調によっては、いかに音の伸びを表すか、響きの減衰なども考えながら、いかに美しい音を作れるか。
そんなことにも腐心しながら、日々演奏しています」と演奏の楽しさと大変さを話してくれた。
「導かれるようなハープとの縁」
「最初は演奏家になるつもりはなかったです。アイルランド音楽が好きで、その音楽につながる楽器としてハープを選び、好きな音楽を好きな人たちと一緒に奏でていたかった。
それと小学生の頃、母が『素敵よ』と習わせたかったハープの記憶が心に残っていたのだと思います。
私がハープを演奏することを母はとても喜んでくれていました」と言葉に想いがつのる。

1stソロアルバム~Voice of Sylva~のジャケット(撮影:本多晃子 / デザイン:黒須俊一郎)
「演奏することへの思い」
「アイリッシュ・ハープを弾き始めたきっかけはアイルランド音楽ですが、周りにはさまざまな音楽の演奏家、諸先輩方がおられて、いろいろなジャンルの音楽や楽器を見聴きする機会に恵まれていました。
演奏に誘ってもらいお仕事をいただくこともあり、興味や経験が徐々に広がっていきました。
今では、アイルランド、スコットランド、北欧の伝統音楽、12世紀~18世紀くらいまでの古楽と呼ばれるヨーロッパの音楽、クラシック、ポップスなどを演奏します。
トルコの曲やジャズもやったことがあります。
ジャンル問わずみたいなところもあり、周りからは、『なんでもやるんだね』とか、『よくそんなにいろいろできるね』といった感想もいただくことがあります。
ミュージシャンはそれぞれ得意なジャンルがあると思いますが、いろんな音楽を演奏する方も多いです。
私もどんな音楽にも対応できる諸先輩方をお手本にしてきました。
私の中では、音楽という一つの軸が通っていて、その軸に複数の糸のようにいろんなジャンルやタイプの音楽が巻きついていくような、上手く言えませんがなんかちょっとそんなイメージでおります。
演奏会が多く曲の研究や練習がたてこむ時もありますが、一つ一つできる限り丁寧に取り組んでいます。
その曲の意味を考えながら、聴いてくださる方の心に響く演奏をしていきたいと思っています」と語る。
田中さんの言葉からアイリッシュ・ハープへの熱い想いが力強く伝わってくる。

ガット弦(素材は羊の腸)のゴシック・ハープ。弦を弾いた時に「馬のいななき(ブレイ)」のような音を鳴らすことができるブレイピンが付いている
「ハーパー(ハーピスト)としてのこれから」
「いろいろあるんですが、まずはアイルランドやスコットランド音楽のレパートリーをどんどん増やし、共演する仲間と深め高め合っていきたい。
また、古楽(18世紀以前のヨーロッパの音楽)にも傾倒しています。13、14世紀くらいの音楽では、ガット弦のゴシック・ハープ(中世後期からルネサンス時代に弾かれていた楽器)を使うことが多いです。
それ以降、18世紀くらいまでの音楽では、本来の形ではルネサンス・ハープやバロック・ハープで演奏されるところ、私はアイリッシュ・ハープで演奏します。
音楽の形式や和音の取り方など、さらなる研鑽が必要と思っています。
そして、地元での演奏会も続けていきます。ポップスやオリジナルを演奏するバンド(Meets Garden Flower)にも所属していて、地元でよくライブをします」と笑顔で話す。

「Meets Garden Flower」 (歌 FUZUKI / ギター、歌 梅村仁 / アイリッシュ・ハープ 田中麻里)

東町カルテット(歌 ほりおみわ / ギター 北川涼 / ハンマーダルシマー 小松﨑健 / アイリッシュ・ハープ 田中麻里)

学園坂商店街にある、レトロ雑貨くるみ屋で販売している「東町カルテット」のオリジナル手ぬぐい (デザイン:くるみ屋店主 菊田健治)

中島祥子猫絵展での演奏風景

「やぎりんカルテット・ケルティカ × デュエット・ヒュ」
前 ヒーリングミュージシャン Hue(ヒュ)(左から ソプラノ:キム・ジヒョン テノール :リュ・ムリョン )
後 左から 読み語り 河向貴子 やぎりんカルテット・ケルティカ( アイリッシュ・フルート、ナイ、ケーナ、訳詞 八木倫明 / チェロ 菅野大雅 / アイリッシュ・ハープ 田中麻里 / ギター 清永アツヨシ )※立川市 女性総合センターホール(アイムホール)での演奏風景
「劇や映像の音楽にも興味ありますが、目下のところは、4年ほど前から携わっている音楽と映像の融合プロジェクト(トリマリアキプロジェクト)への取り組みが課題です」と田中さんのハーパーとしての湧き出る想いは続いていく。

トリマリアキプロジェクト:アイリッシュ・ハープ奏者の田中麻里、写真家の本多晃子、ニッケルハルパ(スゥエーデンの民族楽器)奏者のトリタニタツシの3名で取り組んでいる音楽と映像の融合プロジェクト
■田中麻里 略歴
アイリッシュ・ハープを⻄村光世⽒、坂上真清氏に師事。
1995年よりティン・ホイッスル&アイリッシュ・フルートの安井マリ氏とアイルランド伝統音楽を演奏するグループ「Irish Maries」を結成、ハープ及びバウロン等打楽器を担当。
NHKなどTV番組、各種イベントやライブ、アイリッシュパブにて演奏。C.W.ニコル氏のコンサートツアーに参加。マイク真木、ケイコ・ウォーカー氏らと共演。
2004年~2009年ドイツ・ハンブルグに在住。金属弦のオールド・アイリッシュ・ハープ(クラルサッハ)をStefan Battige、Javier Sainz各氏に師事。
「Historical Harp Society of Ireland」主催のスクールに数回にわたり参加。Siobhan Armstrong、Ann Heymann、Andrew Lawrence-King各氏らの教えを受け、ハープの伝統奏法を学ぶ。
帰国後、ゴシック・ハープを渋川美香里氏に師事。
朗読、歌、アイルランドや北欧の伝統楽器、古楽器、ケーナ、ハンマーダルシマー等打弦楽器やアコーディオン、ギターなど、さまざまなアーティストらと共演、多彩な活動を展開する。
ハープに関するレクチャーコンサートを行うなど、アイリッシュ・ハープの普及活動、後進の指導にも取り組んでいる。
Irish Maries、東町カルテット、 Meets Garden Flower、やぎりんトリオケルティカ メンバー。
Historical Harp Society of Ireland会員。
アイリッシュ・ハープ教室、アイルランドのパーカッション教室主宰。
JEUGIAカルチャーセンターららぽーと立川立飛講師。
2020年ソロアルバム「Voice of Sylva」リリース。
■コンサート情報、レッスン情報
田中麻里HP : https://www.harptanakamari.com/
(取材ライター : 高橋真理)