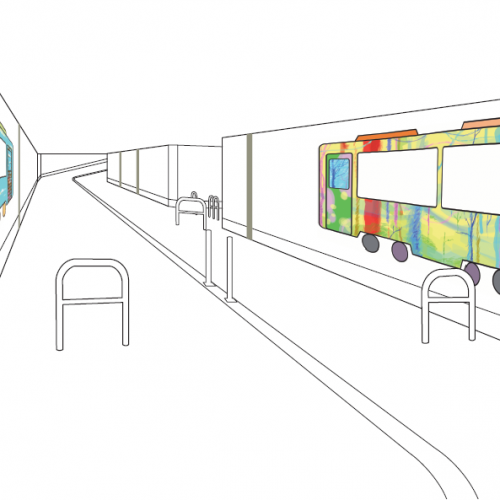東京・立川周辺のART&CULTURE情報
東京・立川周辺のART&CULTURE情報
report

立川市民オペラ2025「ラ・ボエーム」— 愛と夢を奏でる至高のオペラhttps://www.tachikawa-chiikibunka.or.jp/tag/citizenopera/
2025年3月22日(土)・23日(日)、立川市民オペラ2025 歌劇「ラ・ボエーム」が、たましんRISURUホール(立川市市民会館)で開催された。
立川市民オペラでは9年ぶりの演目となるプッチーニの名作 歌劇「ラ・ボエーム」は、初心者でもその魅力に引き込まれる情熱と感動に満ちた物語だ。
この日の舞台では、約100人の出演者たちの力強い歌声と演技が一体となり、まるで19世紀のパリの街並みに自分が溶け込んだような錯覚を覚えた。
2025/03/22 (土)
~2025/03/23 (日)
開催場所
たましんRISURUホール
2025.04.15
「ラ・ボエーム」のあらすじ
物語は4幕により構成され、パリの下町で暮らす若き芸術家たちを中心に展開される。
詩人ロドルフォと、彼の恋人ミミとの切ない愛の物語が主軸だ。
二人は、初めて出会った瞬間から情熱的に愛し合い、その絆が深まるが、ミミが病に倒れることで悲劇が訪れ、ロドルフォとミミの愛は、悲しくも美しい別れを迎える。
一方、ロドルフォの仲間たちも各々の喜びや悩みを抱えており、友情や愛情が交錯し、観客の心を打つ。
全体を通じて、若者たちの夢と現実、希望と絶望が描かれ、感情の豊かな波が観客を包み込む。

クリスマスイブの夜。ロドルフォ、マルチェッロ、ショナール、コッリーネは大家をからかい屋根裏部屋で楽しく大騒ぎ。
4人はカフェへ出かけることとなるが、ロドルフォだけが仕事を終わらせるため部屋に残る。

そこへ、ろうそくの火をもらいにミミが訪れる。

お互い、一目ぼれした二人は皆が待つカフェへ一緒に出かけることとなる。

クリスマス直前の街は賑やか。おもちゃを買ってほしい子供たちと困る親たち。

カフェに入り、5人で楽しく乾杯をしようとした時、パトロンを連れたムゼッタ(マルチェッロの元恋人)が登場。

マルチェッロの気を引こうとあらゆる手段にでるムゼッタ。
必死に気持ちを抑えるマルチェッロと見守る仲間たち。

「足が痛いから靴を買ってきて」とパトロンをその場から立ち去らせるムゼッタ。

ムゼッタへの想いを我慢しきれなくなったマルチェッロがムゼッタを抱きしめ、二人の愛が復活する。

クリスマスが過ぎ、しばらく一緒に暮らしていたロドルフォとミミ。
ロドルフォの様子がおかしいとミミはマルチェッロのところに相談に行く。

その後ロドルフォが起きてきたのでとっさに隠れるミミ。
マルチェッロがミミのことを問いただすとロドルフォは、ミミの病気のこと、そして貧乏な自分ではなく裕福な男性と結婚してほしい、ミミを本気で愛しているからこそそう願う、と打ち明ける。

見つからないよう隠れていたミミはロドルフォの本心を聞き、春になったら別れようと告げる。

その横で、ムゼッタが男性と楽しそうに話をしていたことに嫉妬したマルチェッロとムゼッタはケンカをはじめ、二人は別れてしまう。

別れた恋人のことが忘れられず仕事が手につかない二人。
そんな時、ショナールとコッリーネがご馳走を持ち帰り、宴会がはじまる。

突然ムゼッタが部屋を訪れ、ミミが来ていると告げる。
死期を悟ったミミは最後にロドルフォに会いたかったのだ。
ベッドに横たわったまま、ミミは皆に感謝の気持ちを伝える。

二人きりになった部屋で、ロドルフォとミミは昔の思い出を語り、お互いの気持ちを確かめ合う。
しかし、皆が祈る中、ミミは静かに息を引き取る。
生の感情が伝わる瞬間
オペラは単なる舞台芸術にとどまらず、音楽と演技を通じて感情が観客に直接伝わる特別な体験を提供する。
映画や本では表現しきれない「生の感情」がオペラの中には存在し、観客はその瞬間を肌で感じることができる。
プッチーニの音楽が登場人物の心情を深く表現し、歌声と演技が完璧に融合することで、物語の感動は一層強く響く。
観客は舞台と一体となり、その世界に心から浸ることができるのが舞台鑑賞の特徴だ。

声の専門家によれば、「声そのものはウソをつけない」と言われている。
人間は心でウソをつこうとするが、身体は本能的に正直であり、リアリズムを重んじる。
声は身体から発せられるため、その本音が必ず声に表れる。

つまり、舞台上での歌声や演技は、出演者の内面からの本音を観客に伝える瞬間を作り出す。
この本音が観客に伝わることで、演劇やオペラは私たちの胸を打ち、強い感動を呼び起こすのである。

初めてのオペラでも安心
「オペラってどう楽しむの?」と不安を感じる方も多いだろうが、実際にその場に足を運べば、その不安はすぐに解消されるだろう。
オペラは、歌声、演技、音楽が一体となった総合芸術であり、観客を引き込む力に満ちている。
「ラ・ボエーム」はイタリア語の原語上演ながら、公演によっては字幕がしっかりとサポートしてくれるため、物語をしっかり理解しながら楽しむことができる。
オペラ初心者でも安心してその魅力を堪能でき、映画や本では体験できない「五感で感じる物語」に感動することだろう。

分かりやすい言葉の字幕付きなので四重奏でも物語の内容を理解できる。


3月21日(金)青少年のためのゲネプロ見学会にて、歌劇「ラ・ボエーム」の物語を可愛らしいイラストでわかりやすく説明した親しみやすいパンフレットが子供たち用に配布された。
市民オペラならではの地域一体感
立川市民オペラの魅力は、何と言っても地域との一体感だ。立川市民オペラは、地域の文化振興を目的とした市民による団体で、産・官・民・学の連携により制作・公演されている。
地域社会を支える稀有な形態のイベントであり、地域文化の発展に大きな影響を与えている。
オーディションによって選ばれたプロの声楽家と市民オペラ合唱団、TAMA21交響楽団、児童合唱、助演、オケ賛助者が一丸となって作り上げたこの舞台は、地域住民の熱い情熱が込められている。
出演者たちは、舞台上でのみならず、舞台裏でも地域とつながり、共に芸術を育んでいる。
約一年間の準備期間に全員で積み上げたエネルギーが舞台に乗り移り、観客に伝わる瞬間こそが、この公演の最大の魅力だ。

舞台美術と音楽が作り出す圧倒的な世界観
舞台の美術と照明も見逃せない。豪華なセットがパリの街並みを見事に再現し、物語の情景を鮮明に描き出す。
また、国立音楽大学の学生によるバンダ(小編成アンサンブル)の演奏が、劇中の賑やかなシーンに活気を与え、音楽が劇全体に与える影響の大きさを再認識させてくれる。
音楽と演技が一体となり、日常では味わえないような迫力と感動を、観客は全身で感じることができる。

青少年のための特別な体験
オペラをもっと身近に感じさせてくれる取り組みの一つに、「青少年のためのゲネプロ見学会」というプレイベントが3月21日(金)に実施された。
対象は18歳以下の小中高生とその保護者で約200名が参加。
オペラの舞台裏を実際に見ることで、音楽や演劇の魅力を直に体感できる貴重な機会が提供される。
このような取り組みは、若い世代がオペラを理解し、愛するきっかけとなるとともに、将来のアーティストや観客としての興味を深めるきっかけとなるだろう。
オペラはただのエンターテイメントにとどまらず、感動と教養を育む文化的な体験であり、地域全体を育む力を持っているのだ。


一期一会の感動とその先の未来へ
終演後、「ブラーヴォ!」という掛け声と観客たちの拍手は鳴り止まず、劇場に広がる余韻に包まれた。
「ラ・ボエーム」は、ただのオペラではない。
立川市民オペラの情熱が込められた、地域と共に作り上げた奇跡のような空間だった。
まさに一期一会。観客はその瞬間の感動を胸に、劇場を後にしたことだろう。
オペラを通じて、地域の一体感と芸術の力が深く感じられたこの体験は、永遠に心に残るものとなった。
立川市民オペラの挑戦は、これからも地域文化の象徴として、そしてオペラの新たな可能性を広げる存在として、長く愛され続けるに違いない。
その情熱と努力が、これからも多くの人々に感動を与え、オペラを身近に感じさせてくれることだろう。

■立川市民オペラ2025「ラ・ボエーム」
開催日: 2025年3月22日(土) 16:00開演、3月23日(日) 14:00開演
会場: たましんRISURUホール 大ホール(立川市錦町3-3-20)
指揮: 古谷誠一
演出: 直井研二
キャスト
出演日順(22日、23日)
ミミ:内山歌寿美、石上 朋美
ロドルフォ:金山 京介、澤原 行正
ムゼッタ:栗林瑛利子、田中絵里加
マルチェッロ:的場 正剛、高橋 洋介
ショナール:小仁所良一、香月 健
コッリーネ:杉尾 真吾、小野寺 光
ベノア/アルチンドロ:岡野 守、志村 文彦
パルピニョール:東原 佑弥(両日)
合唱:立川市民オペラ合唱団
管弦楽:TAMA21交響楽団
児童合唱:立川市民オペラ2025児童合唱団(市民公募)
助演:立川市民オペラ2025劇団(市民公募)
バンダ:立川市民オペラ2025バンダ(国立音楽大学有志)
・主催:立川市民オペラの会、(公財)立川市地域文化振興財団
・協働:立川市
・特別協賛:株式会社立飛ホールディングス、岩﨑倉庫株式会社、株式会社いなげや、西武信用金庫
・協力:国立音楽大学
(写真:長澤 直子)
(取材ライター:西野早苗)