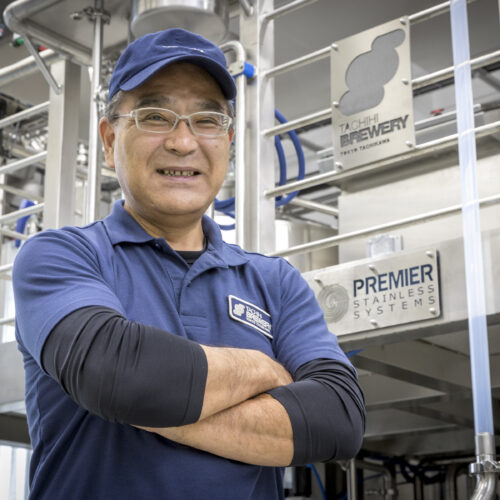東京・立川周辺のART&CULTURE情報
東京・立川周辺のART&CULTURE情報
report

「源氏とあそぶ。源氏をまとう。」 〜若手アーティストや漆芸家と紡ぐ現代の古典〜https://www.tamashinmuseum.org/post/genjimonogatari
1月31日(金)、国文学研究資料館とたましん美術館の共催展示として行われている「源氏物語の新世界―明け暮れ書き読みいとなみおはす―」展に際し、アーティストと研究者によるトークイベントとワークショップ「源氏とあそぶ。源氏をまとう。」が多摩信用金庫本店3階たましん事業支援センターにて行われた。
第一部のトークイベントでは、現在、ないじぇる芸術共創ラボのアーティスト・イン・レジデンス(AIR)として活動中の版画家・芦川瑞季氏と画家・成瀬拓己氏、そして元AIRの漆作家・染谷聡氏が登壇。
「源氏物語」をテーマに、芦川氏と成瀬氏が1年以上にわたる共同ワークショップを通じ、古典が現代アートへと昇華する過程は、心を揺さぶられる予想外の発見に満ちていた。
2025/01/11 (土)
~2025/03/16 (日)
開催場所
たましん美術館
2025.02.14

AIRとは、プロの表現者数名を招聘し、古典籍に触れることで得た感性と知識を創作活動に活かしてもらうプログラム
たましん美術館の受付では、ないじぇる芸術共創ラボのパンフレットを配布しているので是非、入手して欲しい
ないじぇる芸術共創ラボ NIJL Arts Initiative (国文学研究資料館HPより)
芦川瑞季氏の版画作品—表情の奥に隠された葛藤
「古典文学は、決して過去のものではなく、現代の私たちの社会とも密接に関係している。
『源氏物語』から現代のコミュニケーションの在り方についても、新たな視点を得られるのではないか」と語る芦川氏は、「源氏物語」に登場する人物が、感情を抑えながらも内面に強い葛藤を抱えている点に注目。
「源氏物語」の世界を、匿名性の高い現代のデジタル空間と重ね合わせた試みは新鮮で、現代の私たちの内面に深く迫るものがある。
過去に書かれた物語が持つ普遍的な感情の葛藤を、現代の技術と視覚芸術を通じて再解釈したその作品群は、見る者に新たな気づきをもたらすものばかりだ。

芦川氏(左)と成瀬氏(右)は、AIRになるまで「源氏物語」をしっかり読んだことはなかったそう
顔を見せない文化―「源氏物語」とSNS時代の共鳴
芦川氏は、「顔の見えないコミュニケーション」をテーマにし、現代のSNSやインターネット文化と「源氏物語」の関係を探求。
「源氏物語」の登場人物たちは、顔も感情も表にだすことはない。
特に貴族の女性は、御簾越しに姿を見せるか、手紙や和歌のやり取りで自分を表現するしかない。
この「顔を見せない文化」は、現代にも通じる部分がある。
たとえば、SNSでは、ユーザーが自分の写真を投稿せず、文章や絵文字、アイコンで自己表現することが一般的。
これは、「源氏物語」の世界の「御簾の向こう側」と似ているのではないかと感じ、「源氏物語」における「顔の見えない」文化と、現代のコミュニケーションの在り方を重ね合わせながら、「見えない部分をどう表現するか」という問いを投げかけるような作品構成となっている。

見えない部分を想像するー形で感じる「源氏物語」
芦川氏は作品の形状にも意味を持たせている。展示作品は「どの方向からも全てが見えない」ようになっている。
正面から見ると、背後にある絵が隠れ、側面に描かれたイメージが意図的に見えにくい構造。
これは、「源氏物語」における「顔が見えない」状況を視覚的に再現したものだ。
また展示されている作品の形状は、寝殿造の建築様式や、屏風、御簾(みす)といった仕切りを意識。
平安時代の貴族は、直接的なコミュニケーションを避け、間接的な方法で感情を伝えていたため、その空間の感覚を作品のフォルムや配置で表現したという。
まるで能の舞台に足を踏み入れたかのような、現実と過去が交錯する「あわい」の世界。静寂の中、ゆっくりと時間が溶け合い、目の前には千年前の空間が浮かび上がる。

「私が私を笑うとき」パブリックドメインのイメージと、芦川氏が日常で集めた写真やドローイングを組み合わせた、版画に見えない版画作品なのも面白い
芦川瑞季(版画家) ないじぇる芸術共創ラボ|AIR・TIR|芦川瑞季(版画家) (国文学研究資料館HPより)
静岡県生まれ。
2024年現在武蔵野美術大学大学院博士後期課程作品制作研究領域在籍。
版を知覚や認識の外部化と内部化を繰り返すメディアとして捉え、遭遇した風景をリトグラフを用いて制作している。
主な展覧会「TOKASレジデンシー成果展『誰かのシステムがめぐる時』」トーキョーアーツアンドスペース本郷/東京(2023)
「 第3回 PAT in Kyoto 京都版画トリエンナーレ」京都市京セラ美術館/京都(2022)
賞歴は「 第3回 PAT in Kyoto 京都版画トリエンナーレ」ニッシャ印刷財団賞(2022)
「山本鼎版画大賞展」大賞(2021)
2024年4月から国文学研究資料館のアーティスト・イン・レジデンス(AIR)として活動。
成瀬拓巳氏-「源氏香(げんじこう)」の概念を視覚化する

「源氏香によるストラクション」の解説を行う成瀬氏(画像右)
デジタル技術を活用したアート表現を行っており、主にCGやイラストを制作している成瀬氏は、「源氏物語」では「光」や「香り」といった視覚以外の要素が、登場人物の個性や魅力を表現するために用いられていることに着目。
その特徴を「現代のビジュアル表現にどのように組み込めるか」と成瀬氏は考えた。
源氏香とは、香木を聞き分け、その組み合わせを特定するという日本独自の香道の遊びのひとつ。
「源氏物語」では、香りが登場人物の魅力を象徴する重要な要素として描かれている。
例えば、光源氏はその存在自体が「光り輝く」とされ、薫大将は「身体からよい香りがする」と表現。
これは、彼らの内面や個性を象徴する要素であり、視覚以外の感覚が重要視されているともいえる。

右下:「源氏香によるストラクション」制作時、源氏物語に登場する女性たちを香水瓶に見立ててデザイン
左上は、影響を受けたという「源氏香之図」。この作品は是非、館内でじっくりとご覧いただきたい
物語を読み、登場人物たちに花のメタファーを感じた成瀬氏は「香りを視覚化する」というアイデアをもとに、「源氏物語」の登場人物を香水瓶のデザインに落とし込む作品を制作。
それぞれのキャラクターの個性を、香りやボトルの形状、色彩を通じて表現し、視覚的に物語の人物像を伝えようと試みた。
また、「ゲームのように源氏香をやってみたい」という思いから、香水瓶を五十音と組み合わせ、源氏物語の参考書的書物「源氏つまこゑ」の文字の構図で本を作るという斬新な発想は、会場にいる人々を驚かせた。
古典の再解釈—「顔」と表情が語るもの
染谷氏は、“顔の表情”に注目した2人がそれをどう解釈したのか、という点が大変興味深いと指摘。

芦川氏は「源氏物語」では、登場人物たちの表情があまり明確に描かれていないことと、「人笑へ」という言葉が多用されていることに着目。
「特に貴族たちは、自分の感情をむやみに表に出さず、内面の感情を押し隠すことが美徳とされていた。
代わりに、老人や身分の低い人物、動物たちが、感情を表に出す代弁者として登場している。
大河ドラマでも猫が頻繁に登場していたことでも現代にこのメタファーは受け継がれていることがわかる。
これは現在のSNSで、人から笑われることを恐れ、良い部分だけを綺麗に投稿し、匿名のアカウントが率直な感情を発信する構造と重なると感じたそうだ。

左:「紫の上(若紫)」、右:「紫の上(朝顔)」 光源氏に愛されながらも苦悩する女性を表情と色彩で表現
成瀬氏も「源氏物語」に描かれる「顔」と「表情」に注目した。
平安時代の絵巻では、「引目鉤鼻(ひきめかぎばな)」という技法により、登場人物の顔はシンプルに描かれ、感情表現は衣装の色や模様、構図の工夫によって伝えられている。
芸術が上流貴族のものだった当時、装飾こそが身分や内面を映し出す役割を担っていたのだ。
「顔ではなく、周囲の要素によって人物を描く」というこの手法に着目し、現代のデジタル技術で再解釈。
柏木が女三の宮を垣間見て恋に落ちた瞬間を表情豊かに描いた作品や、紫の上の葛藤を色彩と構図で表現した作品では、登場人物に新たな生命が吹き込まれたように感じられる。
「表情には出ない感情の表現」を模索した作品は、見る者に「表情のない顔が語るものは何か」という新たな問いを投げかける。

染谷氏より、「現代の漫画では、キャラクターの感情を伝えるために、目や口の形が細かく描き分けられる。
また、オノマトペ(擬音)や集中線、絵文字といった視覚的な演出も多用されている。
しかし『源氏物語』のような日本の古典絵画では、こうした直接的な感情表現はほとんどない。
表情がないということはある意味読み手側が無限の解釈ができるのではないか」と、考察。
国文学研究資料館副館長 入口敦志氏も、「表情ではなく、登場人物の衣装の模様や色彩、背景の描写によって、感情や身分が示されている。
顔の美醜ではなく、人物に付属するものを詳細に語り、その人の個性や身分を表すこの手法は浮世絵にも通じている。これは日本文学や美術の根底にあるものではないか」と語った。
変わらない古典のカタチと技術の進歩
成瀬氏はデジタル技術を駆使しつつ、日本の伝統的な構図や色彩感覚を取り入れた。
江戸時代の木版画で行われた多色刷りのプロセスをデジタルで再現。
絶妙な色彩を表現している。
入口氏は、「木版→木版刷り→CGと、着彩技術は進化しているが、これら3つの絵を並べると、『源氏物語』そのものではなく、若菜上の場面の“形”が引き継がれていることがわかる」と述べ、この場面を知っていることが「源氏物語」と即座に認識できるのは、時代ごとに様々な解釈や表現がなされ、「長い年月をかけ繋げてきたことを示唆している」とまとめた。

右:「をさなげんじ」の挿絵、 中央:歌川豊国(三世)画「源氏絵物語」の版画、 左:成瀬拓己氏による「若菜上」
成瀬 拓己 (画家) ないじぇる芸術共創ラボ|AIR・TIR|成瀬拓己(画家) (国文学研究資料館HPより)
1997年岐阜生まれ。
多摩美術大学大学院美術研究科博士前期課程美術専攻絵画修了。
2020年FACE2021入選、2021年FACE2022入選
2023年第14回バンフー年賀状コンテスト審査員賞
こいのぼりギャラリーMIDTOWN OPEN THE PARK 2021(2021)
たましん地域貢献スペース企画展「Rebirth」(2022)
FACE展選抜作家小作品展2022(2022)など参加。2024年4月から国文学研究資料館のアーティスト・イン・レジデンス(AIR)として活動。
次に、第二部で漆のワークショップを担当する元AIR染谷聡氏(美術家・漆芸)がAIR活動時のことを当時の映像と共に語った。

染谷 聡 (美術家/漆)ないじぇる芸術共創ラボ|AIR・TIR|染谷 聡(美術家/漆) (国文学研究資料館HPより)
京都市立芸術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。
博士号(美術)取得。京都精華大学、京都芸術大学、沖縄県立芸術大学非常勤講師。
装飾する意味や役割を問うことで、人と自然、歴史、社会のつながりについて探求する。
漆の装飾性を工芸素材にとどまらず、情報や物語を蓄積するメディアとして捉え、それらを手段に制作やリサーチを行う。
2015年京都市芸術新人賞受賞。2021年4月から2023年3月まで国文学研究資料館のアーティスト・イン・レジデンス(AIR)として活動。
「源氏物語」と日本の装飾文化──遊び心と物語性
染谷氏は、幼少期にインドネシアで遺跡や装飾文化に触れた経験から、日本の漆の多様な装飾性に魅了されたという。
漆器は使い込むことで艶を増し、時間とともに表情が変化する。
その経年変化は、登場人物が時とともに成長し、人生が描かれていく「源氏物語」の世界観とも通じるものだ。
「源氏物語」では、人物の心理や感情が装飾や風景として表現されることも多い。
庭に咲く花や調度品の配置が、登場人物の心情を象徴することもある。
こうした視点で物語を読むと、単なる恋愛物語ではなく、より深い意味を持つ作品としての魅力が際立つ。

江戸時代の人々は、漆器や装飾品に「遊び心」を込め、物語を宿らせた。
蒔絵や螺鈿といった技法を駆使し、道具の美しさだけでなく、持ち主の教養や感性を映し出すデザインを生み出した。
こうした「遊び」の文化は、「源氏物語」にも色濃く表れている。
物語の中には、和歌の掛け合いや遊戯、絵巻や装飾品としての展開など、読者が楽しみながら世界観に浸れる仕掛けが随所に見られる。
装飾や道具の描写も細密で、調度品や衣装に込められた意味を読み解くことで、物語の理解がより深まる。
入口氏は「百人一首を見るとわかるが、畳の縁の模様一つとっても身分を示し、天皇が座る場所は特別な禁色が施されるなど、装飾には身分や物語の流れを示す役割がある」と解説。
「読む」と「見る」の交差点—研究者とアーティストの対話
入口氏は、研究者とアーティストの視点の違いが生み出す新たな発見について言及。
「古典文学では表情をほぼ扱わない。研究者は文章を中心に物語を読み解くが、アーティストは視覚的なアプローチから物語の本質に迫る。
今回は、その交差点を感じる機会になった」と語る。
さらに、ヨーロッパのルネサンス絵画が表情豊かな人物描写を発展させていったのに対し、日本の伝統的な絵画では長らく表情が抑えられていたことにも触れ、「江戸時代になると庶民文化が発展し、徐々に個々の感情が絵の中に描かれるようになっていく。
こうした変遷もまた、『源氏物語』の受容の歴史と重なっている」と語った。

画像中央:国文学研究資料館 入口敦志副館長は、アーティストとの共創が生み出す新しい発見を詳細に語った
イベント終盤には、改めて「源氏物語」の持つ力について議論が交わされた。
入口氏は、「古典とは、読む人の時代ごとに新しい解釈を生み出し続けるもの」と話す。
実際に、本展示に参加したアーティストたちは、それぞれ異なる角度から「源氏物語」を捉え、新たな表現へと昇華させた。
「源氏物語は、日本文化の深層に流れる無意識の記憶のようなもの。たとえ全編を読んでいなくても、誰もが知っている。
それこそが、千年を超えて生き続ける物語の力ではないだろうか」と入口氏は締めくくった。
芸術と古典が交差し、新たな視点が生まれたこのトークイベント。「源氏物語」の持つ奥深さを、改めて実感する貴重な機会となった。
切って貼って、古典籍で自由に遊ぶ
第二部のワークショップでは、染谷聡氏(美術家・漆)のもと、参加者たちが古典籍の画像を用いたコラージュと漆工芸を組み合わせた独創的な封筒作りに挑戦。
参加者たちは、古典と現代を結ぶ創作活動を体験した。
国文学研究資料館 木越俊介教授と染谷氏のオープニングトークからスタート。
漆の表現と古典的思考を探求する染谷氏は、日本が誇る漆の耐久性に着目。
漆の保護作用により千年の時を超えて伝えられた「漆紙文書」の存在や、漆の持つ時間を超えた力と、古典を新たな視点で捉える可能性を伝えた。
漆紙文書とは、漆の乾燥を防ぐため、ふた紙として再利用された反故の文書が、漆に保護されることで腐らずに残った古代の文書のこと
ワークショップの手順の説明後、戸惑いながらも古典籍画像シートをハサミで切る、手でちぎるなどして封筒の土台となる用紙に悩みながら貼り付けていく参加者の皆様。
どう組み合わせていくか?コツをつかむとみるみるスピードアップ。
創作スイッチがONになった会場は静かな熱気に包まれた。

漆でコーティングして時間を閉じ込める
休憩をはさみ、第二部では漆の香りがほのかに漂う中、完成したコラージュ封筒に、注意しながら漆を平筆でまんべんなく塗っていく。
漆の塗り重ね方により、仕上がった際の雰囲気が変わってくるそうだ。
吸水性の強い紙でムラにならないよう余分な漆をしっかり拭き取れば完成。
漆でコーティングされ完成したオリジナル封筒は、会場で一旦回収され、一週間ほど預け、乾燥後に個別郵送となった。

漆を塗ると作品の雰囲気がみるみる変わっていく
作品完成後は、お互いの作品を楽しそうに鑑賞しあう場面が多く見られた
芦川氏、成瀬氏もワークショップに参加。
芦川氏は重厚感に満ちた、はちきれそうな勢いを感じるコラージュを生み出し、「本来、破いてはいけないものを破る、切る、ということにいつの間にか夢中になっていた。
様々な意味合いで自由な時間だった」と語っていた。

漆を塗る前のコラージュたち。文字と絵のコントラストが息をのむほど美しい
アフタートークで染谷氏は「古典の新しい残し方」を提案した。
「源氏物語は物語にとどまらず、日本の装飾文化や芸術と深く結びついている。
今回製作した封筒をコピーし、オリジナル源氏物語封筒として使い続けてみてはどうか。
古典籍を現代のメディアコンテンツに置き換えて届けることで、新たな形で残るかもしれない」。
すると、「もったいなくて使えない」とつぶやいていた参加者たちも笑顔に。
もし、自分の作った封筒が1000年後に残っていたら? そう想像するだけで、胸が高鳴った。

参加者からは「楽しかった」「夢中になった」「また参加したい」といった声が寄せられ、手を動かしながら古典に親しむ充実した時間となった。
アーティストトークやワークショップをきっかけに、改めて美術館へ足を運びたくなった人も多い。
古典文学は、決して遠い過去のものではなく、現代と響き合っている。この展示で、その不思議な感覚を味わってほしい。

2年前に製作した時間封筒をコピーし、新たに封筒をつくってみた
経年変化を楽しめるのはこの封筒の醍醐味。2年前の同ワークショップを動画で味わおう
→令和4年9月17日、AIR染谷聡さんを講師に迎え開催した「ものがたりを保存する ~漆でつくる時間封筒(タイムカプセル)~」の様子
ないじぇるの活動・イベント | ものがたりを保存する ~漆でつくる時間封筒(タイムカプセル)~ (国文学研究資料館HPより)
■展示「源氏物語の新世界―明け暮れ書き読みいとなみおはす―」
共催展示「源氏物語の新世界ー明け暮れ書き読みいとなみおはすー」 – 催し物 | 国文学研究資料館
• 会期:2025年1月11日(土)~3月16日(日)
• 場所:たましん美術館(東京都立川市緑町3-4)
• 利用時間:10:00~18:00(入館は17:30まで)
• 休館日:月曜(祝日を除く)
• 入館料:一般500円、高校生・大学生300円、以下無料
●国文学研究資料館研究者によるギャラリートーク <毎回異なる研究者による解説は必見>
日時:2025年1月11日(土)、1月25日(土)、2月8日(土)、2月22日(土)の全4回 各回午後2時30分~午後3時
場所:たましん美術館展示室内
問い合わせ先
国文学研究資料館 学術情報課社会連携係
TEL:050-5533-2984 FAX:042-526-8606
E-mail:jigyou@nijl.ac.jp
(取材ライター:西野 早苗)