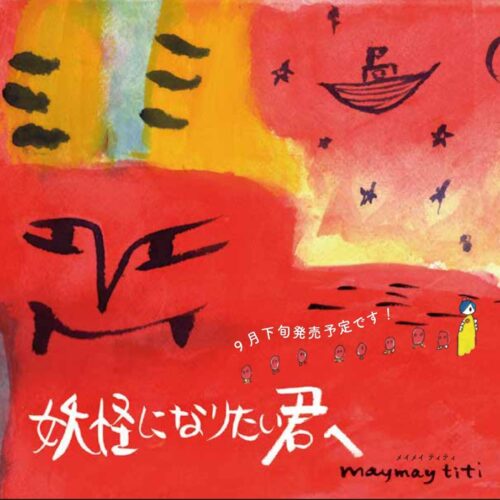まず初めに、立川を拠点にされた経緯を教えていただけますか。
大学受験に失敗して落ち込んでた20歳ぐらい頃、新宿の西口でヒッピーたちがいっぱい集まるところにいたら「新宿から西に30キロぐらい行ったところに素晴らしい場所があるよ」という話を聞き、興味を持ちました。そこでアトリエを作ろうという話になり、仲間達と昭島の米軍ハウスに住み、結婚を機に立川の米軍ハウス(現「BONZE工房」)へ引っ越しました。
長年立川で活動する中で、この街が育んでくれたものは、何よりも人との出会いです。いろんな方々と交流を深める中で、立川という場所が持つ魅力と可能性に気づかされました。特に、立川ロータリークラブの方々からの依頼で、駅前の飛行機少年像「風に向かって」を手がけられたことはとても嬉しかったですね。立川を象徴する像としてご紹介いただく機会があること、作品を通じて街に貢献できることを誇りに感じています。私にとって第二のふるさとである立川が、これからも魅力的な街であってほしいですね。美術館やギャラリーが増え、病院やオフィスビルにもアートが溶け込むことで、立川は今よりもさらに魅力的な街になると思います。

立川の飛行機少年像「風に向かって」にはどのような思いがあるのでしょうか?
立川にはかつて飛行場がありましたが、そのことを知る人が少なくなっています。そこで、立川の歴史の一部として「飛行機少年像」を作ることで、「ここにはかつて飛行場があったんだ」という記憶を形にして残しました。過去をただ懐かしむだけでなく深く掘り下げ、大事なものを拾い上げていくと、新しい価値を生み出すことができる。それがまさに「飛行機少年像」です。
未来のことを考えることも大事ですが、過去から学び取れることは本当にたくさんあります。特に地方では、古いお寺や神社に残る彫り物や壁画を見ると、その街の歴史を感じることができます。それらを眺めながら当時の様子を想像するだけでも、とても面白いですよ。

アートとまちづくりの関係をどのようにお考えですか?
アートは、単なる飾りではなく人の心を動かし、街に息吹を与えるものです。音楽も彫刻、絵画も同じです。街のどこにどんなアートを置くかによって、人の感じ方が変わり、コミュニケーションも生まれます。だからこそ、アートを通じて、街に「愛」や「優しさ」を増やしていくことが大切です。
日本全国、いろんな地域で作品を作りましたが、まず大切にしているのは現地主義です。実際にその街を歩き回り、街並みや人々の様子を肌で感じることで、自然とさまざまなイメージが浮かんできます。そこからデッサンを重ね、作品へと形にしていきます。私は、建築の勉強していたので、家を建てるのと同じ方法でアート作品をつくっています。
長年活動する中で感じるのは、強い「自己」を築く大切さです。自己をしっかりと持つことで、環境や状況に流されず、本当に大切なものを見極めることができます。自分をしっかり持っていることが優しさの源となり、その優しさが作品に反映され、見る人に感動を与える作品を生み出す力になります。そう考えると、創作の原動力は「愛」であり、人形作家だった私の妻も同じことを言っていました。やはり、作品には優しさや愛が込められていないと、どこか空虚なものになってしまう。これは農業でも同じことが言えます。作物に声をかけ、愛情を込めて育て、「美味しくなれ」と願いながら作る。その思いがあるからこそ、人に喜んでもらえるものになるのです。
地域に根ざしたアートを作る際に大切にしていることは何でしょうか?
過去を受け継ぎながら未来へとつなげることを意識しています。そのために、子供たちの姿や地域の記憶を形にすることを大切にしていますね。
街を歩くと、子供たちの姿がほとんどなく、学校や塾へ通い、大人たちだけが行き交う光景が広がっていることがあります。そこで、子供たちが元気に遊び回る風景を街に取り戻したいと考えました。子供たちは未来の象徴であり、彼らが生き生きと過ごせる環境をつくることで、街全体に活気が生まれます。かつての日本では、子供たちが自由に遊び、大人たちは遠くから見守りながら、ときには叱り、ときには関わることで、地域のつながりが生まれていました。そうした環境をもう一度アートを通してつくることが、まちづくりにおいて重要だと考えています。
また、街の歴史や文化を形として残すことも大切ですね。かつて産業で栄えた地域が時代の変化とともに姿を変え、工場がなくなり、新たな建物が建つことがあります。しかし、その土地に根付いていた精神や誇りを後世に伝えるため、街の記憶を刻んだシンボルを制作することがあります。例えば、かつての産業の名残を感じられるオブジェを街の一角に設置し、歴史を感じられる景観づくりを意識しました。
(取材ライター:Me Time Japan in Tama )
人生で影響を受けた【私の三冊】を教えてください
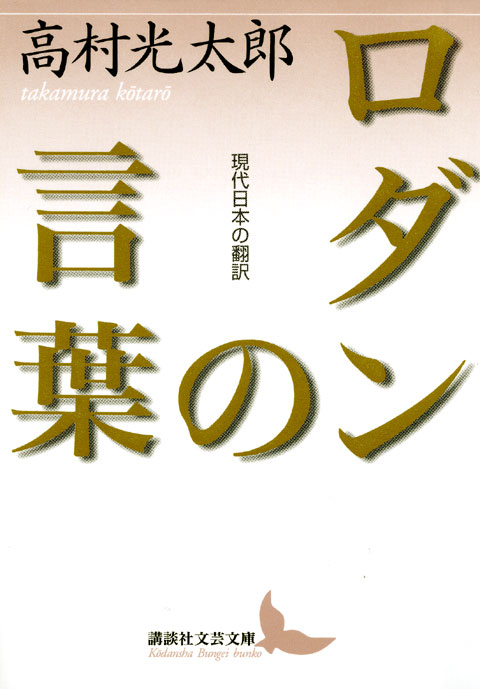
「正直な労働者のように君たちの仕事をやり遂げよ」「自分の感ずるところを表現するに決してためらうな」など、ロダンの死後、遺稿として発表された「若き芸術家達に」という筆記に感銘を受けました。高校の美術部の先輩に薦められた一冊で、長年経った今も特別な感慨があります。自分の思いと共鳴する先達の言葉が、困難な時期を乗り越えさせ、芸術家としての自信を持ち続ける力となりました。
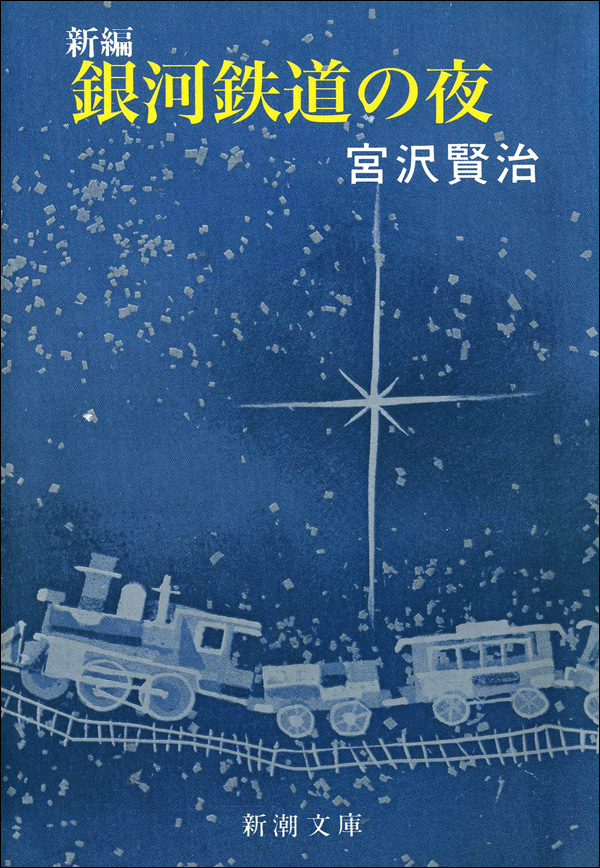
上京して浪人していた頃、先輩や仲間たちが大絶賛していた作家だったので、自然と興味が湧きました。九州・大分出身の自分にとって、南方的な考え方に親しみがあり、そんな自分が北方信仰に触れることで、また新たな哲学的な視点を得ることができました。
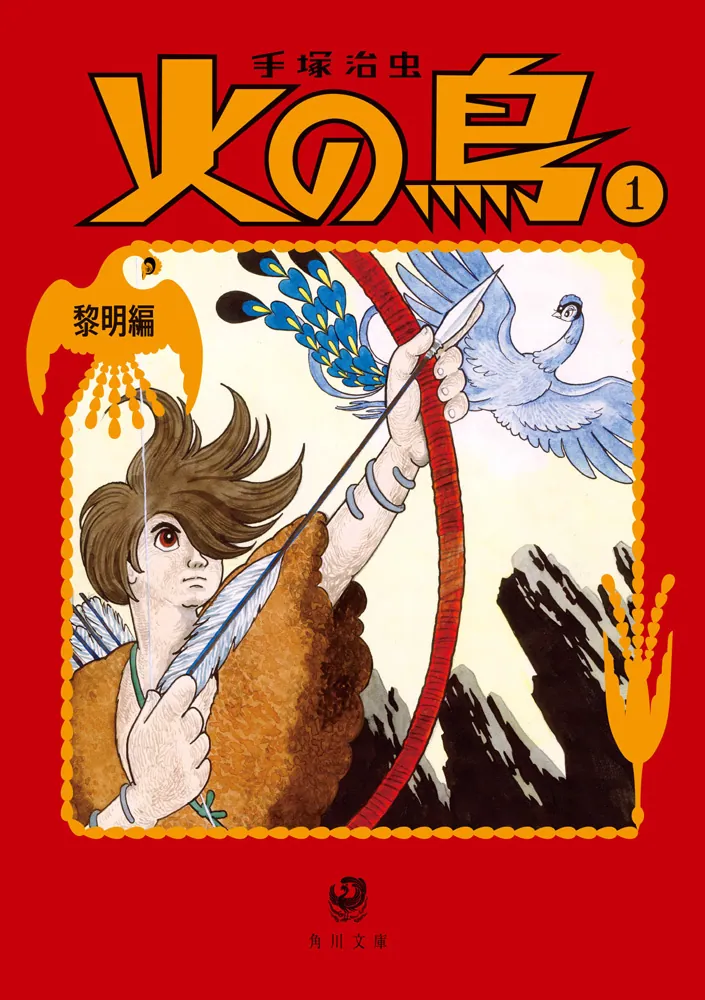
手塚治虫の『火の鳥』は、私の人生に大きな影響を与えた作品です。本作は「永遠の命とは何か」という問いを通じて、時代を超えて変わらぬものや、命と魂が受け継がれる意味を描いています。このテーマは、私の創作活動にも深く通じています。 赤川BONZEの作品制作においても、形として残るものの奥にある精神や想いを次の世代へ伝えることを大切にしており、その哲学を『火の鳥』から学びました。