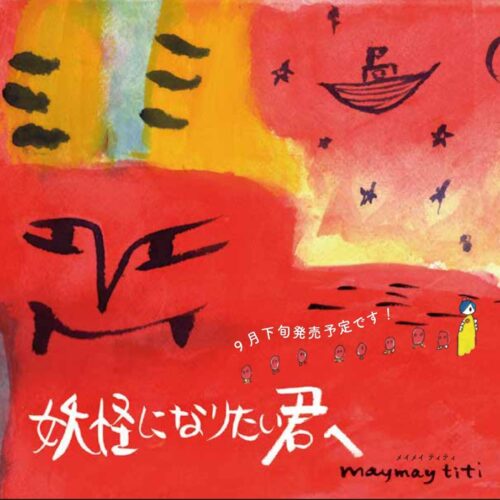東京・立川周辺のART&CULTURE情報
東京・立川周辺のART&CULTURE情報
report

市民が作った文化の砦「日野市の図書館 歩みと建築」
「歳月を経るほど、美しくなる」。そんな建物が日野市にあることをご存知だろうか。
JR中央線の豊田駅南口から徒歩7分、浅川を望む崖の上に建つ日野市立中央図書館。
周りの緑に馴染む落ち着いた色の煉瓦が貼られた壁、光が降り注ぐ吹き抜けの空間、子どもが本を読みやすい机と椅子。
多くの市民が今も日常的に使う、とても心地良い空間だ。
日野にこんな素敵な図書館があるのは偶然ではない。
「市民のための図書館」の実現に奔走した人たちがいた。
「親しみやすく入りやすい図書館」「歳月を経るほど美しくなる建物」。
それが初代館長が建築家に伝えた注文だった。
応えた建築家は図書館建築の名手、鬼頭梓(きとうあずさ)。
建物は後に「DOCOMOMO JAPAN 日本におけるモダン・ムーブメントの建築」に選定。
開館から50年経った今、国の登録有形文化財への登録へ向けての動きが進んでいる。
2025.02.21

機運高まる講演会
2月1日(土)、日野市立中央図書館で「日野市の図書館 歩みと建築」という講演会が行われた。
日野市が誇る図書館建築の意義について、市民と共有し、価値を発信する機運を盛り上げようというイベントだ。
講演を行ったのは、講談師の田辺凌鶴(たなべりょうかく)氏と、建築家・鬼頭梓について研究する神奈川大学教授・京都工芸繊維大学名誉教授の松隈洋(まつくまひろし)氏の2人。
会場には応募した参加者50人が集まった。
申込みは先着順ですぐに埋まったという。
会の始めに、日野市立中央図書館の登録有形文化財への登録への動きについて、説明があった。
登録有形文化財とは、建てられてから50年を経過した歴史的建造物のうち、一定の評価を得たものを文化財として登録し、保存と活用が促される、文化庁の制度だ。
一定の評価とは、「造形の規範となっているもの」「再現することが容易でないもの」などが挙げられている。
日野市立中央図書館の、登録に値する価値について、今回の講演会で語られた。

日本の公共図書館の原点
最初に、田辺凌鶴氏による講談「日野の移動図書館ひまわり号」が行われた。
講談とは、講談師が高座におかれた小さな机の前に座り、歴史にちなんだ読み物や、最近ではオリジナルの物語を、観衆に向かって独特の調子で読み上げる、日本の伝統話芸の一つだ。
今回、田辺氏が語ったのは、日野の図書館の歩みにまつわる物語だ。
田辺氏は、学生時代に豊田駅から大学に通っており、「この街には思い入れがある」という。
張り扇と呼ばれる小道具を手に持ち、釈台(机)を叩いてパパンという音を響かせながら、テンポ良く語り始めた。

日野の図書館は、昭和40年(1965)に、移動図書館「ひまわり号」からスタートした。
自動車の荷台にたくさんの本を積み、団地の広場など市民がいる場所に行って車を停めて、集まってきた市民に本を貸し出すのだ。
初代館長である前川恒雄(まえかわつねお)は、イギリスの図書館を視察し、市民のための図書館がどうあるべきか、について高い理想を持っていた。
当時の日本は、読書も図書館も一般市民に身近な存在ではない時代で、まだ図書館がない市町村が多かった。
最初から立派な建物を造るのではなく、こちらから市民の中に入っていけるよう移動式で始めて、市民の中で自然と必要になってから建物を建てよう、という意図だった。
前川館長も車に乗り込み、市中を周った。
しかし初めは、移動図書館がやって来ても集まる人は少なかった。
それでも続けるうちに徐々に本を借りる人が増え、「ひまわり号」の周りには多くの大人や子どもが集まった。
高座に坐る田辺氏は、借りた本を手にし笑顔で図書館を利用する市民の様子を、巧みな話術で生き生きと語った。

「ひまわり号」という名前は、日野を毎日周ることから、付けられたという。
しかし、本を借りる人が増えるにつれ、市民からは「常設の図書館が欲しい」という要望が出されるようになった。
それに応えて児童図書館や分館が造られていき、いよいよ中央図書館が建設されることになった。
昭和48年(1973年)4月28日に日野市立中央図書館が開館。
それまでの図書館は、カウンターで申し込んで書庫から出してもらわなければ本を読めない図書館が多かった。
日野市立中央図書館では、館内に並べられた本棚から市民が自由に本を手に取り読むことができる。
今では当たり前の光景だが、本がまだ高価な時代で、一般市民が気軽に読むものではなかったのだ。
また、市民が読みたい本が日野市の図書館になかった場合、近隣の市から取り寄せるリクエストサービスも実現した。
前川恒雄館長は、市民のための図書館を目指し、結果多くの日野市民が読書を身近に楽しむようになった。
日野市立中央図書館は、日本の公共図書館のモデルとして注目され、その思想が全国に広がっていった。
ちなみに「ひまわり号」は今も日野市内を周り続けている。
理想の図書館建築
続いて、松隈洋氏による講演が行われた。
テーマは「建築家・鬼頭梓が図書館建築に求めたもの」。
鬼頭梓も松隈氏も、日本のモダニズム建築の巨匠と呼ばれる前川國男に建築を学んだ。
前川國男は、世界文化遺産にもなっている国立西洋美術館を設計したル・コルビュジエの弟子にあたる建築家で、日本中で多くの美術館や文化施設を設計した。
松隈氏は、すでに亡くなっている前川國男や鬼頭梓の建築思想について研究を続けている。

鬼頭梓は、山梨県立図書館や東北大学図書館、山口県立図書館、日本建築学会賞を受賞した東京経済大学図書館などの設計を手掛け、図書館建築の名手と呼ばれている。
鬼頭は学生時代に太平洋戦争の終戦を迎え、破壊された街の光景を目にして、「人々の生活の拠点を作りたい」という想いを持っていたという。
一方、中央図書館の設計を任せる建築家を探していた前川恒雄館長は、国分寺にある東京経済大学図書館を見に行き、鬼頭に中央図書館の設計を依頼した。
鬼頭は、日野の移動図書館に乗り込み、車に集まってきて熱心に本を借りる市民の姿に感銘を受けたという。
前川館長が鬼頭に依頼したのは、「親しみやすく入りやすい」「利用しやすく、働きやすい」「歳月を経るほど美しくなる」などの条件を満たす図書館建築だった。
後に「人生を賭けた挑戦だった」と語った鬼頭が実現したのが今の建物だ。
その特長は、実際に行ってみると良く分かる。

外観は、自然豊かな日野市の風景に馴染む煉瓦の壁。
時とともに煉瓦の一つ一つの色が微妙に変わり、味わい深くなっている。
館内に入ってすぐに、2階までの吹き抜けがあり、大きなガラス窓から浅川沿いの風景が見える。
吹き抜けは、設計段階で前川館長に反対されたのだが、鬼頭が説得して実現させた。
前川館長は、吹き抜けにするとその分本を置く書庫が減る、と考えたのだ。
しかし実際に建物ができて、開放的な空間を見て一番喜んでくれたという。

松隈氏が特に注目するのが、図書館の前の道路から通学中の子ども達が館内の児童書のコーナーを覗き見ることができる大きな窓だ。
きっと多くの子ども達が図書館に寄って行ったのだろう。
「館内の向こうの窓を通して、庭の緑が見えるのも素晴らしい」と熱く語った。

鬼頭は、館内の本棚や机や椅子も日野市立中央図書館のために設計した。
本棚は、下段の本を手に取りやすいように斜めになっている。
フロア手前の棚は館内を見渡せるように低く、奥の棚は本がたくさん入るように高い。
児童書のコーナーにある、子ども向けの机と椅子はその形がとても可愛いらしい。
机は子どもが本を姿勢良く読めるよう傾斜と滑り止めがついていて、椅子は子どもが座りやすい高さ。
「熱心に本を読む子どもの姿がとても良い」と松隈氏は語った。

市民に愛され続ける図書館へ
今回の講演会には、日野市の大坪冬彦市長と、波戸尚子副市長も参加していた。
「日野市の図書館は市民の誇りであり、市民と市がともに作った文化である」「建物を登録有形文化財へ登録する準備を進める」と講演会で力強く挨拶をした。
質疑の時間には、「中学生の頃からずっとこの図書館に通っている」という女性の参加者がいた。
二階にあるレファレンス室が、落ち着いた雰囲気で特に気に入っているという。
外から見た二階の壁と窓ガラスから見えるライトは、鬼頭梓が後に記した本「建築家の自由〜鬼頭梓と図書館建築」の表紙の写真にもなっている。

現在、全国で書店が次々に姿を消し、書店が一つもない「書店ゼロ」の市区町村は全国で約3割にのぼる。
インターネットが普及した現代でも、だれもが気軽に情報に接することができるということは、国民の知る権利につながり、民主主義の根幹にも関わる。
市民のために造られ、今も市民が愛する図書館を永く残すことは、日本の文化を支えることに他ならない。
(取材ライター:いけさん)