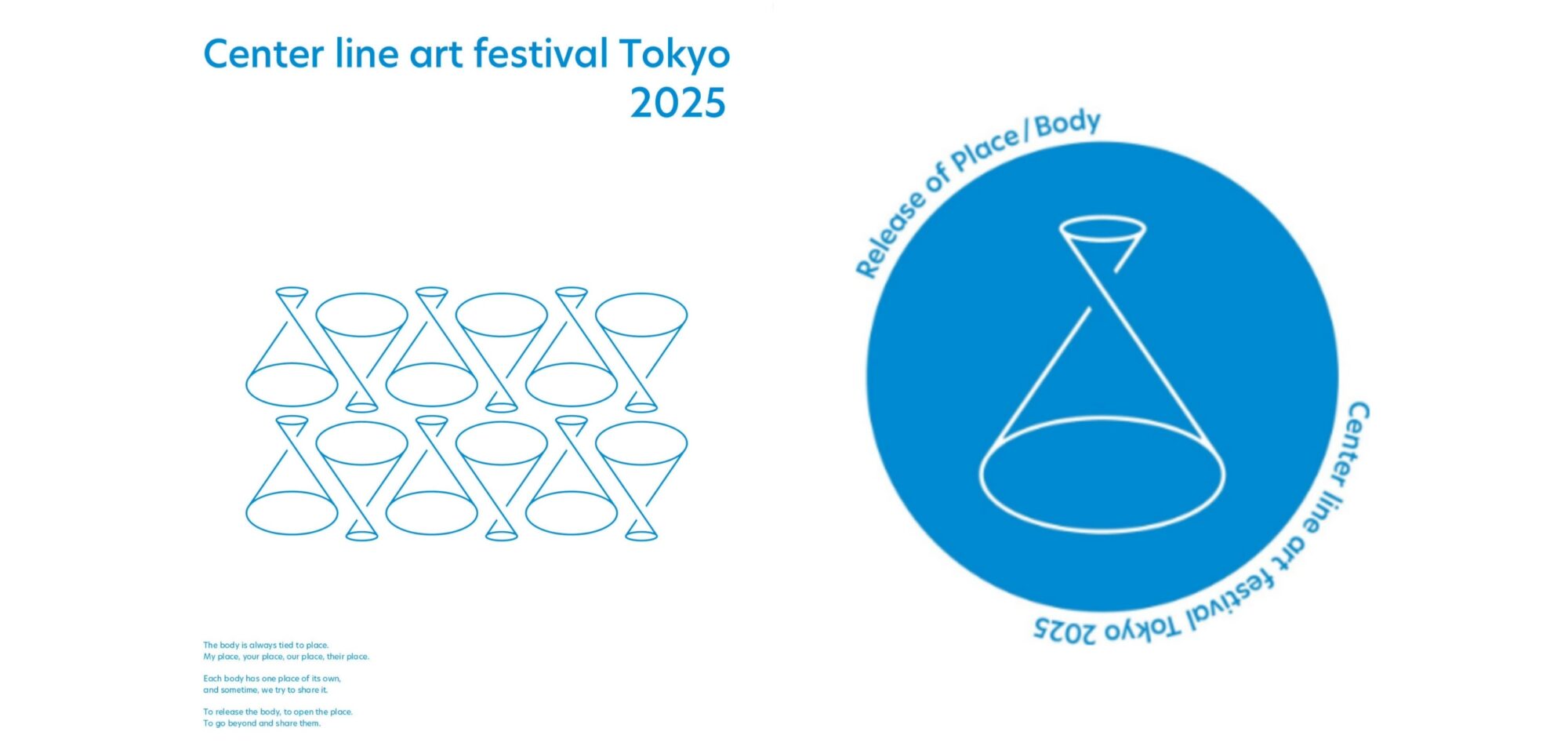
 東京・立川周辺のART&CULTURE情報
東京・立川周辺のART&CULTURE情報
news
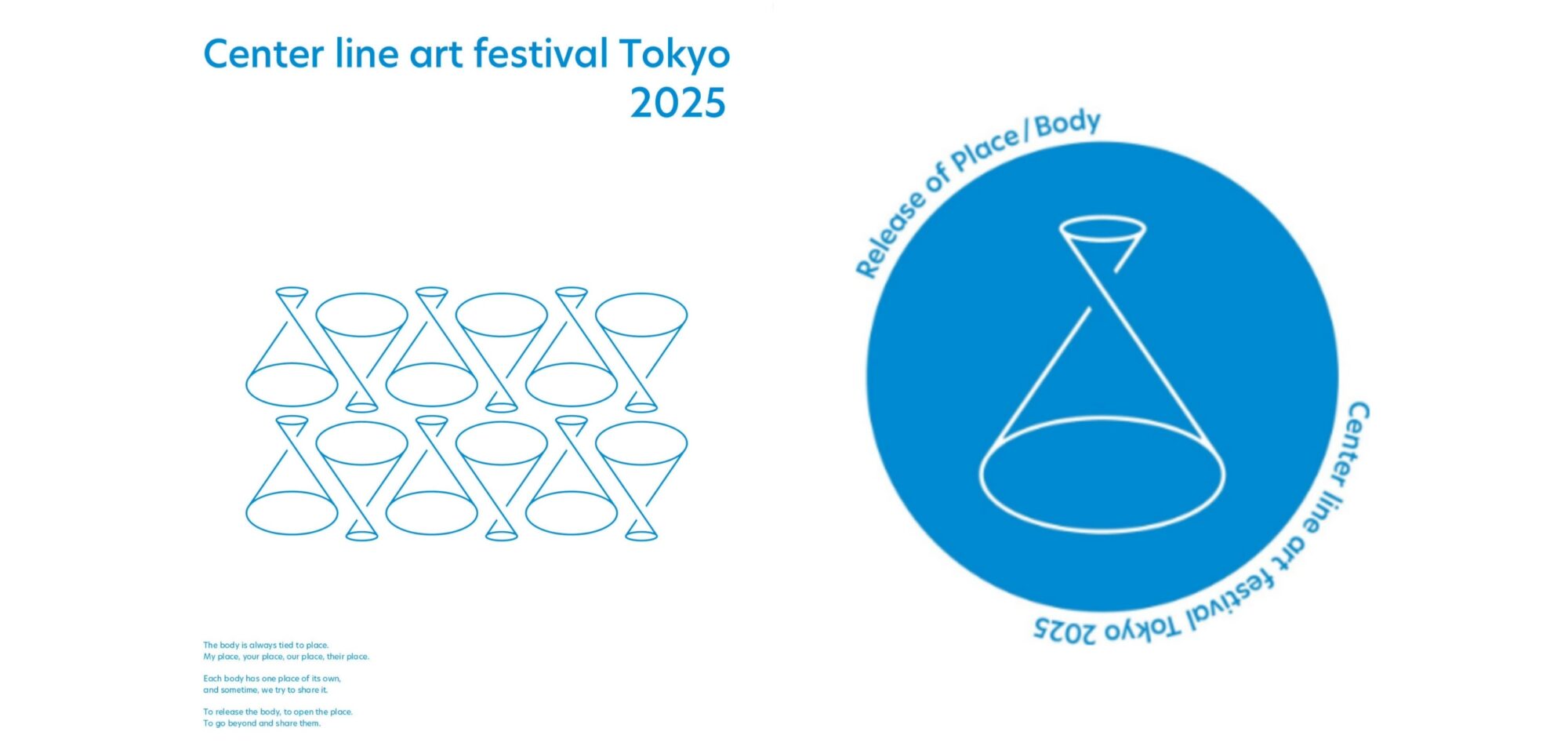
「Center line art festival Tokyo 2025」開催
「Center line art festival Tokyo 2025 中央線芸術祭」は2021年から始まり、今年で5回目となる回遊型のアートフェスティバルである。
「アートで毎日が旅になる」というコンセプトのもと、回を重ねるごとに参加アーティスト数も増え、開催エリアも広がっている。
今回取材したのは9月23日から始まった国立・国分寺・小平エリアで行われているプログラム。主催者である一般社団法人Co-production of art Works-M代表アートディレクターの三浦宏之さん、そして、制作の田中麻美さんに話を聞いた。
会期:2025年9月11日(木)〜11月3日(月・祝)
開催エリア : 中央線の中野駅から国立駅間にある周辺施設
2025.10.06
「ボランティアの方たちに支えられています」
「私は、基本的には全エリアを管理しています。
アーティストの方が在廊されていれば、何かしらのサポートをし、市民ボランティア『Clafters』の方たちとは受付やアテンドなど会場の運営を行っています。
また、事務局のメンバーにはさらに深くフェスティバルの企画や運営に関わりたいと、『Clafters』での活動を経て参加してくれているメンバーもいます」。
毎年、新しい市民ボランティア『Clafters』の募集をしているが、毎回参加する顔馴染の『Clafters』も多くいるという。
「初年度を観て、ちょこっとだけ手伝いたいと思ったの、ちょこっとずつ関わりたいの。気軽に行ける感じがいい」。
「今年の春からボランティアに参加しています。
大学生なので、なかなかアート業界に関われる機会がない。
それでも探していたら運よく見つけて、快く受け入れてもらえた。
ボランティアなので自分が観に行かないモノに触れられたり、子供たちの純粋な疑問が面白かったり、自分が感じたことや提案したことも取り入れてくれる環境も心地よくて、続けていきたいです」と会場にいた『Clafters』の面々は思い思いの参加理由を話す。
「運営として、私たちが関わることで」
「アートって解らないから、関わりにくく構えられてしまいやすい。
けれど、そうではなく誰でも見ることができ楽しめる。
そこで一つでもいいから言葉を交わせて、『自分達も絵をかいてみようかな』とか『何か作ってみようかな』という想いや気持ちに繋がっていけばいいなと思っています。
そして、アートに関わることで『Clafters』の人たちが感じたり、思ったり、『やってみたい』という気持ちが実現できる場所になっていって欲しいです。
日常では体験できないような出会いや感覚を繋げていけるような立ち位置でフェスティバルを盛り上げていけたらいいなと思っています」。

「年々、フェスティバルの参加者や場所は増えています。
地域としてのエリアは2~3年は変わらないのですが、今年は、奥多摩でプレイベントを開催し、少しずつエリアの拡大は進んでいます。
観に行く側のお客様のことを考えると、一駅だけや一駅間を歩いて回れるような距離でエリアをずらしながら開催していくこと、フェスティバルを通じて身近な生活圏内を旅するように、街を新たに発見していけたら楽しいよねということ、一つのエリアにはとどまらずに複数のエリアにまたぐ回遊型ということは初年度からみんなで大切にしています。
また、地域の方との繋がりや、地域の方の活動に興味を持ってもらう機会として、アートを通じての社会貢献をどのような形で提示していけるのかなと考えています」と田中さん。
フェスティバルを楽しむ気持ちが伝わってくる。
取材先の一橋学園駅にある「iru」ではmomoka_nakayama 個展「Washing the Secrets, Gently」が開催されていた。
「Washing the Secrets, Gently」
「なんでもシェアしちゃう時代に、『ひっそり心に留めておくという良さがあるよね』みたいなことを、ここで体験していってもらえたら」とmomokaさんは言う。

Washing the Secrets, Gentlyイワシの大群のようにシャボン玉を回遊させた。自分で息を吹きかけられるチェーンもある
「元々、人はどういう動きに生き物を感じるのかという研究とかをしていたんです。
The Parasitic Animacy単純な動きなんですけれど自由に予期せぬ動きをする。ソフトロボティクスなので触って感じて欲しい」。
小さな子供たちの感じ方も面白かったという。

左:Anthro Scope触れるモノの音を録音することできる。 右:The Parasitic Animacy黒いロープの様なモノが不規則な動きをする
「触り心地の音を拾って録音できるようにしたAnthro Scopeは記憶を録音するとかはありますけれど、全部その心に秘めているということを大切にしたくて。
考え事をしながらその時の音とか、こっそり考えていることを『いわなくてもいいから音にだけはしてみる』とか。
『言わなくてもいいけど触れてみる』そういうことをしながら『言わなくていいけど内に秘めてるもの』は大切にねっていうことを伝えることができたらな」と作品に込めた思いを話してくれた。
「Center line art festival Tokyo 2025 中央線芸術祭」は人と街をアートで繋ぐ回遊型のアートフェスティバル。
田中さんと一緒に、アートディレクター三浦宏之さんが待つ、国分寺市にある沖本家住宅 和館に向かった。
「Center line art festival Tokyo の始まり」
「僕は舞台芸術の仕事を主にしていたんですが、コロナの時に、アーティストが活動の場を失っていくことに対して強いショックを受けたんです。
自分たちで継続していける場所を自分たちで作っていく必要があるんじゃないかと思った。
そんな時、新宿方面に行く中央線に乗ったんです、緊急事態宣言の時だったので、普段は混んでいるはずの中央線の箱の中に、僕とあと2人くらいしか乗っていなくて、不思議な世界に紛れ込んだ気がしたんです。
箱の一番端っこ、多分シルバーシートだったと思うのですが、初老のご婦人が乗っていて、緊急事態宣言で皆気が張っている中で、お昼寝というか電車に揺られながら、うつらうつらしているところに午後の光がさしこんだりしていて絵画的というか美しい風景だなと思ったんです。
中央線っていつも混んでいて良いイメージはなかったんですが、とてもきれいなローカ線なんだと思ったんです。
子供の頃のローカル線の緩い感じを中央線でも感じたんです。
少し遡るのですが、島々を旅するように巡る瀬戸内芸術祭や新潟の大地の芸術祭に参加したことがあって、地方の大型回遊型アートフェスティバルは東京にはないなと。
その時、中央線の駅を巡る芸術祭をやろうかな、中央線ならできるのではないかと思ったのがきっかけです」。
「芸術祭とアーティスト」
「本来は有名なアーティストの方に参加してもらうほうが、集客や収益的にはいいのかもしれないのですが、そうではなく、誰しもが知っているではなく、地道に活動し独特の活動をしているアーティストの方に参加をお願いしています。
最初は、私の知人から始まり人づてに広がっていきました。初年度から毎年8名ほどアーティスト公募もしていて、毎年50名~60名くらいの応募があります。
昨年からは国際公募にし、海外からの応募も増えてきました。
継続して参加していただいているアーティストの方もいます。
人との繋がりや出会いでアーティストの方は増えていっています」。
沖本家住宅 和館では、岩渕貞太「リバーズ・エッジ」(2021年から始まった即興シリーズ第5弾)が開催されていた。

※撮影禁止の為ClafT2025 / Iwabuchi Teita リバーズ・エッジを参照

アートディレクターの三浦宏之さんとClafT2025参加アーティストのDaniel Monsalveさん
「10年後にむけて」
「初年度は東京駅から青梅までとは言ってはいたのですが、5年間やってきたなかで中央線沿線の西側の魅力に気が付いたんです。
新宿から先の中心部とは少し違う、ちょっとローカルな芸術祭にしていこうかなと考えています。
分離させるということはしたくはないので23区も入れつつ中心は西側で。
アートセンターみたいなものができたらいいなと思ってます。
最初に感じたローカルの良さをどうやって残していけるのか、再開発などとの共存。人との繋がりや街の在り方を『Center line art festival Tokyo』を通して考えていきたい」と穏やかに話してくれた。
田中さんと三浦さんの話を聞いた帰り道、いつもの見慣れた景色の中をゆっくりと歩いた。
■Center line art festival Tokyo 2025
国立・国分寺・小平エリア開催スケジュール
10月7日〜13日 阿目虎南 個展・パフォーマンス 「神に愛された孤高の天才舞踏家、その外郭と内燃」
10月10日〜13日 藤生百音個展「余白に鳥はうたう」
10月10日〜13日 三浦晃写真展「Musashino Landscape」

■お問い合わせ
HP : ClafT / TOP
(取材ライター: 高橋真理)





